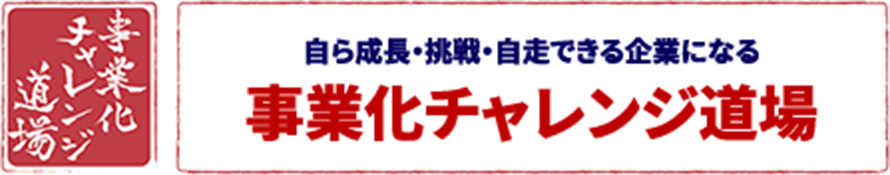泰興物産株式会社事業内容:プラスチック射出成形、試作及び試作金型製造、IoT
従業員数:10名
所在地:東京都立川市錦町6-18-1

開発品 de-Sebum(デ・シーバム)

会社の将来に危機感を持ち再び参加
泰興物産株式会社は現在、プラスチック製品やIoT製品の企画から量産までを一貫して対応できる製造会社だが、ここまでの道のりを一言で表すのは難しい。
1975年創業で、当初はプラスチック射出成形品の量産請負が主力。その後、自社製品を作りたいと事業化チャレンジ道場参加を経て、2013年に独自の化粧ブラシを開発・販売する。また2016年には、金型製作の内製化も始める。2018年からは、無給電で動作するセンサーなどのIoT機器も手がけ、事業の幅を拡大してきた。
当社の転機は、2006年。プラスチック射出成形の量産品だけでは会社の将来が拓けないと危機感を持った丸田陽氏(現社長)と丸田智子氏(現取締役開発部長)が、事業化チャレンジ道場の前身である「ものづくりデザイン道場」に参加。この時は、基本的な開発手法は学んだものの、プラスチック射出成形という従来業務から発想が抜け出せなかったため新製品開発は断念。しかし「自社製品を何とか手がけたい」「製品の提案力を身につけたい」という思いは変わらず、2011年に再び事業化チャレンジ道場の門をたたいた。
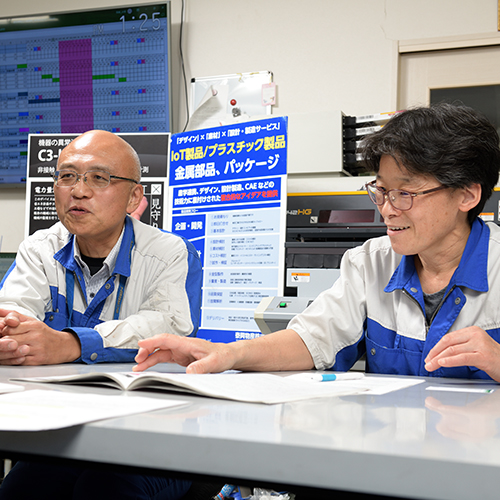
代表取締役 丸田陽氏(左)
開発部部長 丸田智子氏(右)

考え方が変わり、見える景色が違ってくる
2回目の事業化チャレンジ道場参加時は、もともと行っていた化粧ブラシの仕入れ販売にヒントを得て、「男性向け洗顔ブラシ」を考案した。折しも女子サッカーW杯で「なでしこジャパン」が優勝、国民栄誉賞の副賞で「熊野筆」が注目されていた頃。当社の取引先に熊野筆メーカーがあり、自社の強みを活かして今までにない形のブラシを作ろうと考えた。
2年目の事業化実践道場に入ると、この製品企画をブラシュアップするとともに、いくつかの課題に向き合うことになる。東日本大震災や円高等の影響で本業の受注が減少するなか、当社として初めて「ものづくり補助金」を申請し、試作品や金型代に充当した。
また、この製品の特徴の一つに、ブラシ部分に角があり、鼻脇等の狭い部分にまでブラシの毛先が届くというメリットがある。担当のプロジェクトマネージャーから「世の中にない形と機能があるのだから、特許を取った方がよい」との助言もあり、特許取得に取り組むことになったが、本業のかたわら丸田取締役が公社知的財産総合センターに通い詰め、特許出願書類を自力で全て書き上げたというから、この製品にかけた意気込みがわかる。
早速、出来上がった試作品を展示会に出展すると、化粧品メーカーや異業種からも問い合わせが相次ぐなど反響を呼んだため、製品化を決意。2013年には、自社ブランド「de-Sebum(デ・シーバム)」として、独自の洗顔ブラシを開発・販売するとともに、大手化粧品会社にODM採用され、年間で8,000本の出荷に成功する。
その後、営業や販促活動を地道に行い、化粧品販売会社からも好感触を得たが、商品の取扱量など商流も想定と異なり、「このままこの事業を本格化すると、大量に生産し販売する化粧品関連メーカーにならなくてはならない。従業員10名規模のこの会社では、そこまでやり切れない。」(丸田社長)と「やらないこと」を決断、従来からの化粧品メーカーとの取引は維持し、ブラシの特注対応などは手がけつつも、現在は自社の「広告塔」の役割となっている。展示会などで出展するときも、まずこの化粧ブラシが目を引き、そこから商談が始まるケースもあるという。ただ、自社製品を持った意味はそれ以上に大きい。
「例えば下請けだと、他社との競合上厳しい見積もりを相手に出さなくてはいけない。開発案件ならば、自分たちの今まで培ってきたものづくりのノウハウを活かして交渉ができる。一回ものづくりを経験すると、考え方が変わり、見える景色が違ってくる。」(丸田社長)
その後、射出成形機用の金型製作事業を始めたことも、自分たちで金型を起こせることで、スピーディな試作やいろいろな素材にトライできるというメリットはもとより、より自信を持って自社のものづくりをアピールできるようになったという。


開発品 de-Sebum

培った製品づくりが、“お客のために”
射出成形品、化粧ブラシ、金型製作と業容を徐々に拡大してきたものの、何かもの足りなさを感じて悶々としていたある日、丸田取締役が、母校でもある東京工業高等専門学校(八王子市)に行った折、電子工学科水戸慎一郎工学博士の研究室で、あるデモンストレーションを見る。この出会いが、新たな製品開発の始まりだった。
無給電で動作するIoT電流センサー『C3-less電力センサー』は、東京高専との産学連携で4年間かけて研究・開発した製品。同センサーは、既存設備の電源コードに簡単に後付けでき、コードからの漏れ磁束から電気を得るため、電池を使用しない。設備の電源を切れない企業や、低コストでIoTを導入したい企業にも利用しやすいというメリットがある。
この製品の使い勝手をさらにブラッシュアップする狙いと、社内の若手技術者の育成もにらんで、2017年には入社1~2年の若手3名により、三回目の事業化チャレンジ道場に参加。その年のCEATECに出展すると、すぐさま大手建設会社から声がかかり、参入の足掛かりとなった。
同社にとっては、エレクトロニクス分野への初の本格進出となったが、改良の過程で電子回路の開発も自社で行うことになりそのノウハウも蓄積、さらには入社したばかりの長男の丸田哲郎氏(開発部エンジニアリング・マネージャー)も設計・開発に大きく関与した。
「今や3DCADや3Dプリンタのおかげで設計が容易になり、電子回路設計も自社で行うことが可能になった。これで企画から量産まで一貫した対応ができ、お客様の製品づくりを形のないところからサポートするという夢に一歩近づけた。」(丸田社長)という。現在は、IoTセンサなど回路設計開発が売り上げの3割まで拡大している。電子回路設計と筐体設計製造、この2つを1つの会社でできるという強みを今後さらに強化していく考えだ。
事業化チャレンジ道場から始まった自社開発の製品づくり。企業によっては、その製品コンセプトに沿って第二弾、第三弾の新製品を市場に投入し、自社ブランドとして強化する企業もある。しかし当社は、その製品づくりのノウハウを基に、「お客様の製品づくり」へと発想を展開したことで、業容が拡大し本業も活性化させてきた。
「自社製品を持つと、お客の気持ちがわかる。だからこんなものが欲しいと言われると、何とかして実現しようと、とことん考えるようになった。顧客の要望に応えようとしているうちに、少しずつ業容が広がり、企業体質が強化されることになった。」(丸田社長)
“製品づくりノウハウの再生産”ともいえるところがユニークだ。

4年間かけて開発したC3-less電力センサー

手を動かして作ることを大事に
同社の従業員数は現在10名。平均年齢が25歳と若い。また社長、取締役含めて、高専出身者が多い。
「若い人が多いので、職務もフレキシブルにしていろいろな経験をさせつつ、“自分で考え、手を動かしてみよう”と。とはいえ若い人たちに支えられている会社なので、私たちが最年長で皆から年寄り扱いですよ。」(丸田社長)と笑う。トップダウンというより、一緒に何かおもしろいことをやろうという社内の雰囲気が感じられる。
自称“何でも屋”だから、さまざまな要望が持ちかけられる。が、時には思うような結果が出ない案件もある。
「まずはやってみる。失敗したら、一度立ち止まって、どうすればできるのかを考える。それでまた、手を動かしてやってみる。失敗も多いけれど、できたときは本当に楽しいです。」(丸田取締役)
「ものづくりでは、試行錯誤するところが、一番おもしろいし、大切ですね。」(丸田社長)
ビジネスについてやりとりするときの社長と取締役開発部長の二人の様子も、当意即妙、愉快さとワクワク感にあふれている。二人の化学反応から、また次のビジネスのネタが生まれる予感がする。(2024年12月取材)
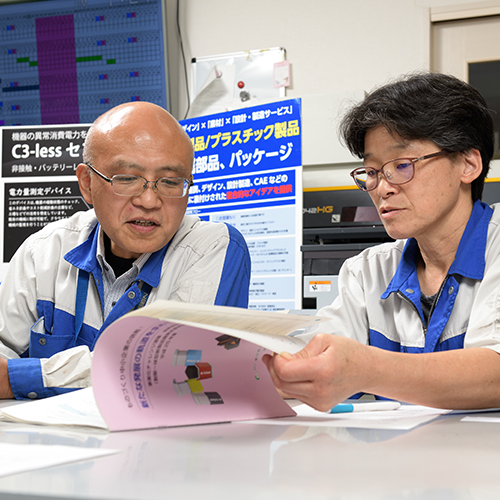
当時を振り返る丸田夫妻
文章/城南支社
撮影/堀内 まさひろ
会社概要
| 参加者名 | 代表取締役 丸田 陽氏 開発部部長 丸田 智子氏 他 1名 (事業化チャレンジ道場2回目の参加者) |
|---|---|
| 経営者の参加 | あり |
| 資本金 | 1,000万円 |
| TEL | 042-522-7168 |
| FAX | 042-528-1726 |
| URL | https://iot-tokyo.com/ |